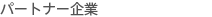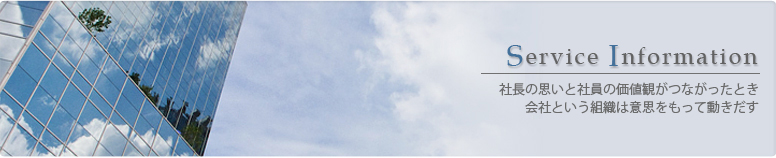

- まず、社長の「事業への思い」と「社員への思い」をお聞きします。そして、それが社員に対し適切でわかりやすいことばで表わされているのか、事業戦略にどう結びついてるのかを確認、検証します。
- 次に、社員の方からも「仕事への思い」と「会社への思い」をお聞きします。基本的には直接インタビューさせていただきますが、場合によっては組織診断ツール(アンケートサーベイ形式)を併用することもあります。
- 両者の思いから現状をとらえ、生じているずれとそれを発生させている原因を探ります。
- ラウンドテーブル(対等な関係で自由に発言する場)やパネルディスカッションのような対話形式の手法を使い、社長の「思い」と社員の「価値観」をひとつにしたものを「クレド」という形で簡潔にかつ具体的なことばとしてまとめていきます。ここでのファシリテーションが弊社サービスのひとつの特徴です。
(くわしくは下記 –弊社サービスの特徴Ⅰ- をご参照ください) - あわせて、そのクレドを有効にかつ継続的に機能させることができるような環境と組織風土をどのようにつくっていくのかを検討します。「思い」のずれとなっていた原因を取り除き、社員がクレドを自分のもの(マイクレド)として自ら行動にうつすことができるよう、ツールや機会、しくみや組織構造など広い分野にわたる検討を、総合的に行っていきます。クレドを机上の空論として陳腐化させない取り組みが、弊社のふたつめの特徴です。
(くわしくは下記 –弊社サービスの特徴Ⅱ- をご参照ください) - 各種ツールや仕組みを実際に開発します。頭で理解することばとあわせて、視覚からうったえつづけて腹に落としていくことができるようデザインにもこだわります。
(くわしくは下記 –弊社サービスの特徴Ⅲ- をご参照ください) - 施策を実施していきます。社員の受け止め方と変化をみながら、計画を調整しつつ慎重にすすめていきます。
- 持続的成長のために、定期的な診断、調査の実施をお勧めしています。
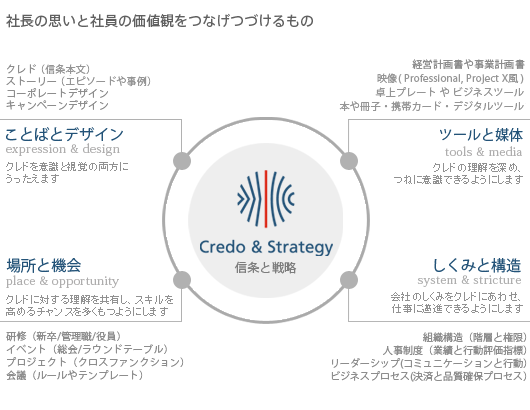

クレドをつくり、一時的に広報するだけではクレドは機能してくれません。むしろどんどん陳腐化し、実態とかい離したむなしいものになっていってしまいます。クレド&ストラテジーは「社長の思いと社員の価値観がつながり続け 会社という組織が意思をもって動き続けられる」よう、つぎの三つのポイントを大切に考えコンサルティングサービスしています。
- Ⅰ.社長と社員の合作でクレドを策定
- 社長からの押し付けに見えてしまっては、せっかくの「思い」も通じないものです。過去の「良い仲間」や「充実していた時間」「大きな達成感を味わった仕事」などを思い出して共有するとともに、未来を「一緒に」「なにを大切に」「どうつくっていくのか」をとことん話し合っていただきます。ただ、ここではファシリテーションがその成否を大きく左右します。参加者が役割を認識して「本気」になるにはどうしたらよいか、ざまざまな「思い」をどう一つの方向にまとめていくか、「思い」と「不平・不満」「阻害要因」をどう切り分けるか、コンサルタントの力の発揮しどころとなります。
- Ⅱ.継続的実行基盤を整備
- 実施に当たっては、クレドと事業の現実との間で、どのようなずれが生じてしまっているかを検証します。そしてそれを少しずつでも解消していくにはなにが必要なのか、業務プロセス・人財(スキル)・組織風土・組織構造、それぞれの観点から見ていき解決策をつくっていきます。そうして現実とクレドのずれを解消していこうとする意思を社員に見せながら、つねに現場でクレドを意識するようなしくみとあわせて、その浸透と納得を社員に図っていきます。管理職のマネジメントや人事評価も重要です。クレドと相違がないような制度と意識の醸成をおこないます。
- Ⅲ.デザインと視覚的表現
- ことばだけでなく視覚にも訴えかけることを重要視しています。オフィス、工場といった職場はもとより、提案書のテンプレートなどの営業ツール、カレンダーやホームページなどにも、クレドを表すデザインを随所に取り入れます。そうすることで、ふと判断を迷ったりしたときなどに、クレドが視覚に入って意識できるようになります。ふかい理解を促すものとしては、ロールモデルとなる人物の仕事や流儀を紹介したり、象徴的なプロジェクトの成功要因を探るようなストーリーを映像化、文章化して、機会があるごとに見るようにすることも効果があります。